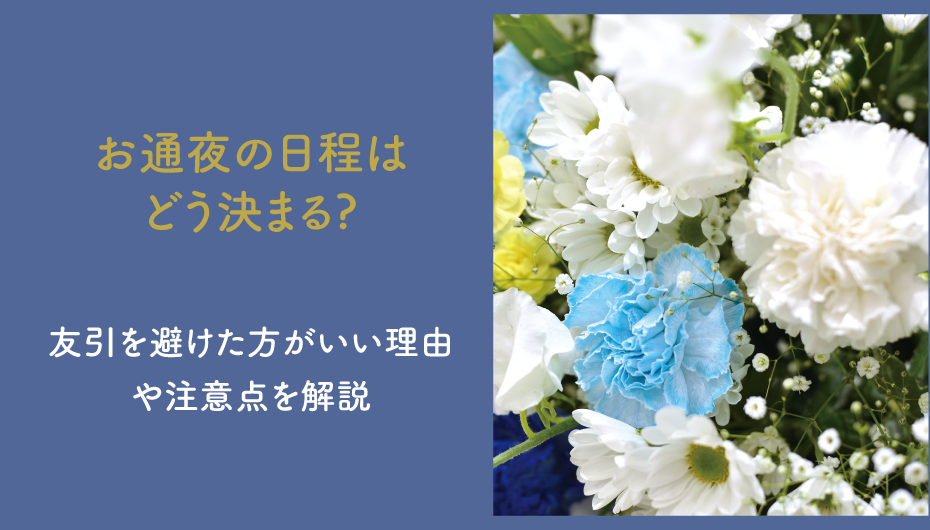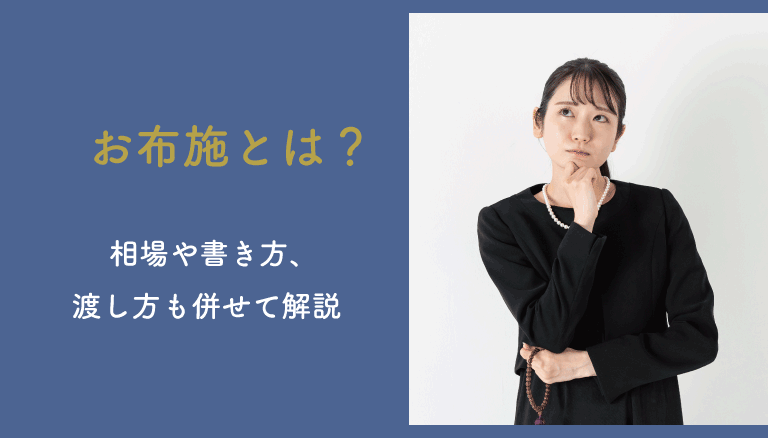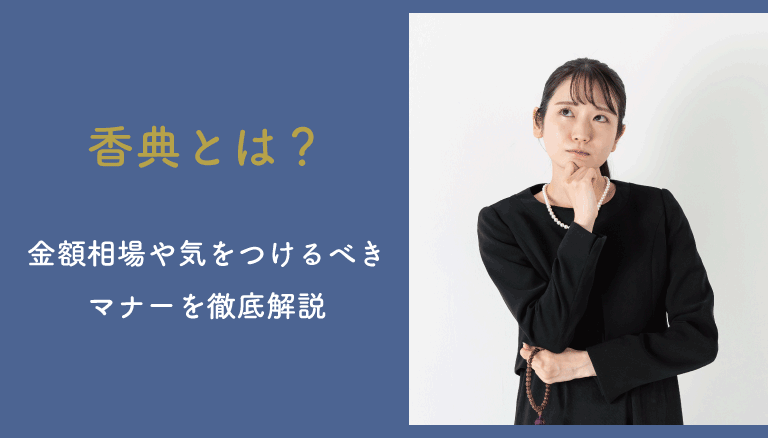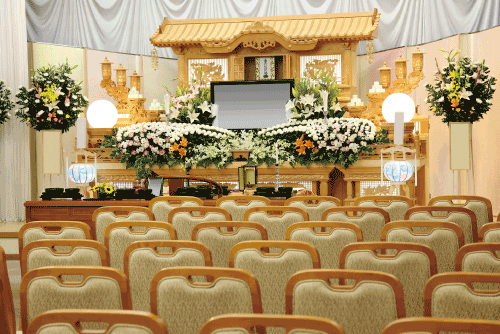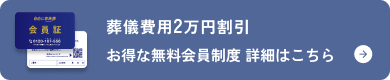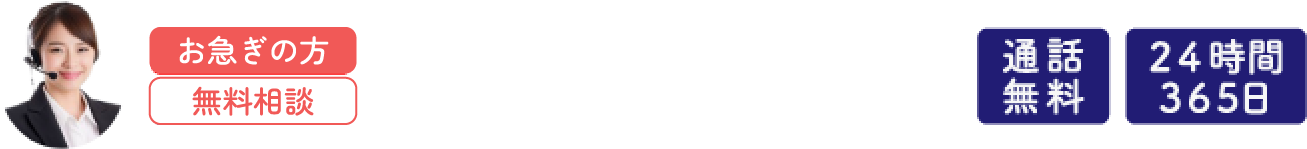大切な方を送る最初の一歩:スムーズにお通夜の日程を決めるために
ご家族や親しい方が亡くなられた際、心痛の中にも、葬儀に向けて様々な準備を進める必要があります。その中でも、まず最初に取り掛かるべき重要な事柄がお通夜の日程の決定です。葬儀社の担当者と相談しながら、お通夜と告別式の日取り、火葬場の予約、そして宗教者(僧侶など)の手配を進めていくことが求められます。
この記事では、身近な方が亡くなった場合に、どのようにしてお通夜の日程を決めていくべきかについて詳しく解説します。亡くなられた時間帯による違い、友引を避けると考えられる理由、さらにお通夜を行う上での注意点についてもご説明いたしますので、ぜひ参考になさってください。
お通夜はいつ行うのが一般的?
お通夜は、通常、故人が亡くなった日の翌日の夕方から夜にかけて執り行われます。しかし、これはあくまで一般的な目安であり、葬儀場や火葬場の予約状況、亡くなられた時間、菩提寺や宗教者の都合によって、日程は変動することがあります。ここでは、お通夜と告別式の日程について、より具体的に見ていきましょう。
お通夜のタイミング
お通夜の期日は、ご家族やご親族が逝去された時点で決定するのが一般的です。主に喪主となる方が葬儀社の担当者と相談し、詳細を詰めていきます。多くの場合、亡くなった日の翌日にお通夜が営まれますが、地域によっては当日に行われるケースも見られます。
また、亡くなった翌日に必ずしも火葬場の予約が取れるとは限りません。火葬場が定休日の場合や、予約が集中している際には、火葬場の状況や宗教者のスケジュールに合わせて告別式の日程が決まるため、それに合わせてお通夜の日程を調整する必要があります。
さらに、ご親族が遠方に居住しており、翌日にすぐに駆けつけることが難しい場合も、日程調整が必要となることがあります。お通夜の日にちは法律で定められているわけではありませんので、それぞれの状況に合わせて最適な日を選ぶことが重要です。
亡くなられた時間帯による考慮
早朝の場合: 午前5時や6時といった早い時間に逝去された場合、葬儀場や火葬場の空き状況、宗教者の都合、そしてご親族の予定が全て整えば、その日の夕方以降にお通夜を行うことも可能です。
ただし、お通夜やお葬式を急いで行う必要はありません。早朝に亡くなられたとしても、まずはご遺体をご自宅などに安置し、落ち着いて準備を進めた上で、翌日にお通夜を行うという選択肢も十分にあります。
また、当日のお通夜が難しい場合には、「仮通夜」という形で故人を偲ぶこともできます。仮通夜とは、亡くなった当日に集まることができる近親者のみで行う儀式です。 当日の調整が難しい場合は仮通夜を行い、翌日以降に一般の弔問客も参列できる本通夜を行うのも、一つの方法と言えるでしょう。
夜中の場合: 夜10時から深夜2時頃に亡くなられた場合、葬儀会社に連絡が取れるのであれば、翌日(日付が変わっていれば当日)にお通夜を行うことも考えられます。
しかし、これも葬儀場や火葬場の空き状況、ご親族や宗教者の都合がつくことが前提となります。葬儀社とご自身の都合だけで日程を決めるのではなく、関係者と調整することが大切です。
告別式の日程
告別式の日程は、お通夜の日程と並行して決定します。多くの場合、お通夜の翌日に告別式が執り行われますが、これも絶対的な決まりではありません。 葬儀場や火葬場の予約状況、ご親族、宗教者の都合などを総合的に考慮し、最適な日程を選択することが重要です。
お通夜の日程で「友引」を避ける考え方
お通夜の日程を決める際には、葬儀場や火葬場の空き状況やご親族の予定に加えて、もう一つ考慮されることがあります。それが「友引の日」を避けるという考え方です。 友引は、中国から伝わった「六曜(ろくよう)」という暦注の一つで、他に先勝、先負、仏滅、大安、赤口があります。
本来、六曜は中国発祥であり、仏教の儀式とは直接的な関係はありません。そのため、友引にお通夜を行うこと自体に宗教的な問題はありません。神道やキリスト教においても同様です。しかし、仏教の一部の宗派では友引を避けるという考え方があります。また、一般的に日本社会においては、結婚式を「大安」や「友引」に行い、弔事は「仏滅」など、六曜に基づいて冠婚葬祭の日取りを決める習慣が根強く残っています。
友引は「友を引く」という字面から、結婚式には縁起が良いとされています。しかし、弔事においては「故人に親しかった友人をあの世に引き寄せてしまう」という意味合いで、友引にお通夜や葬儀を避ける方も少なくありません。
このように、仏事と六曜に直接的な関連性はないものの、日本では六曜を気にする人が多いため、慣習的に友引は避けた方が良いと言われることが多いのです。 また、六曜を気にする人が多いため、友引の日に休業する火葬場も存在します。そのため、火葬場の予約という観点からも、友引を避けることが賢明な判断となる場合があります。
お通夜の日程を決める際の注意点
大切な方が亡くなられた直後は、深い悲しみの中で、様々な決定をしなければならないため、精神的な負担が大きいかもしれません。しかし、特に喪主となった方は、故人を滞りなく見送るために、冷静に物事を進めていくことが大切です。
ここでは、お通夜の日程を決める際に留意すべき点について解説します。
死後24時間以内の火葬は法律で禁止
お通夜や告別式の日程は基本的に自由に決めることができますが、火葬に関しては、法律によって死後24時間を経過するまで行うことができません。これは、墓地、埋葬等に関する法律第三条に定められているもので、妊娠7か月未満の死産を除き、亡くなってから24時間以内は火葬することが禁じられています。
ただし、この法律はあくまで火葬のタイミングを制限するものであり、お通夜の日程を直接的に制約するものではありません。火葬が死後24時間以降に行われるのであれば、早朝に亡くなった場合でも、当日にお通夜を行うことは可能です。
速やかに葬儀会社に連絡を
ご家族やご親族が亡くなられた場合、まず最初に行うべきことは葬儀会社への連絡です。ご親族の都合が調整できたとしても、葬儀場や火葬場の予約が取れていなければ、葬儀を執り行うことはできません。特に年末年始や火葬場の休業日明けは予約が集中するため、できるだけ早く連絡を取ることが重要です。
しかし、喪主をはじめとするご家族は、故人の逝去直後に多くの手続きや対応に追われ、すぐに連絡を取ることが難しい場合もあります。そのため、事前に葬儀会社に相談しておくことをお勧めします。事前に準備すべきことや、いざという時の流れを把握しておけば、慌てることなく対応できるでしょう。
参列者と宗教者のスケジュール確認
葬儀場や火葬場の予約が確保できたら、参列予定者と宗教者のスケジュールを確認します。まず、ご家族やご親族には電話やメールなどで速やかに連絡を取り、都合の良い日程を調整しましょう。その他の友人知人や仕事関係者には、連絡を取りまとめてもらう代表者を一人選び、その方に連絡を依頼するとスムーズです。
また、宗教者については、菩提寺に連絡を取り、僧侶の都合を確認します。菩提寺がない場合は、葬儀会社に相談することで、宗教者を紹介してもらうことができます。
地域の風習やしきたりを確認
お通夜やお葬式は、地域によって様々な風習やしきたりが存在します。例えば、葬儀の前に火葬を行う地域もあれば、葬儀の後に行う地域もあります。日程を決める前に、地域の慣習を確認しておくことが大切です。
まとめ
お通夜は亡くなった翌日に、告別式はその翌日に行うのが一般的ですが、葬儀場や火葬場の予約状況、ご親族の都合などによって、予定通りに進められないこともあります。多くの方にとって、お通夜やお葬式の喪主を務めることは、人生において何度も経験することではありません。そのため、いざという時に何をすべきかを事前に把握しておかないと、安心して故人を見送ることは難しいでしょう。
自由に家族葬は、ただ安いだけでなく年間20,000件以上の葬儀実績を誇るグループとして、終活サポートや葬儀の事前相談から、葬儀後のアフターサポート(樹木葬、海洋葬儀などのご供養や法事・仏壇・仏具の手配、墓地・墓石、遺品整理など)まで幅広く対応しています。
お通夜や葬儀に関して不安なことがある場合は、自由に家族葬に相談ください。24時間365日お客様のお問い合わせにお応えします。