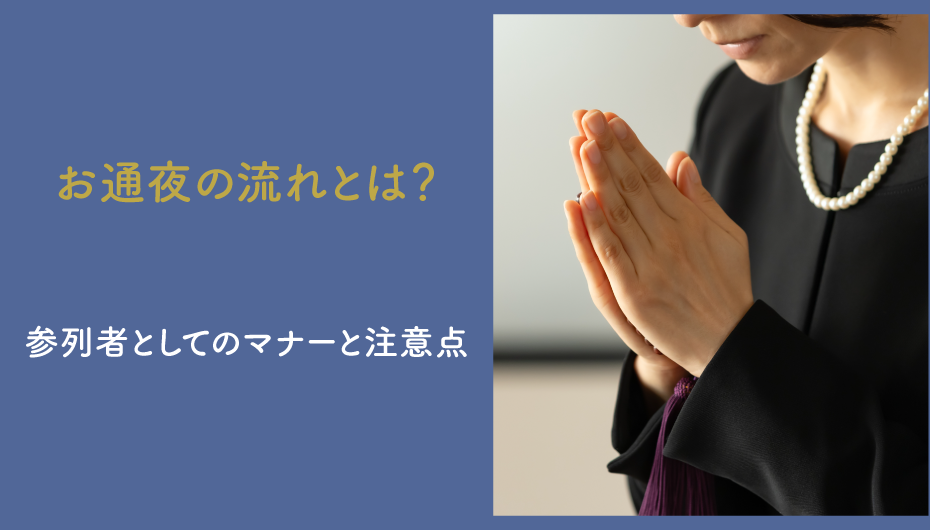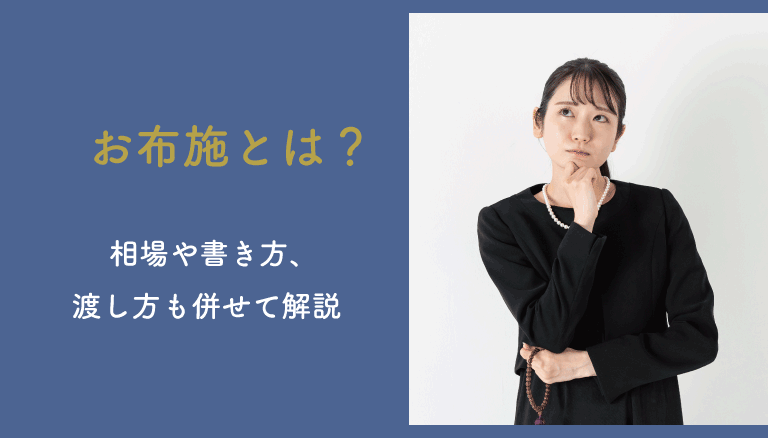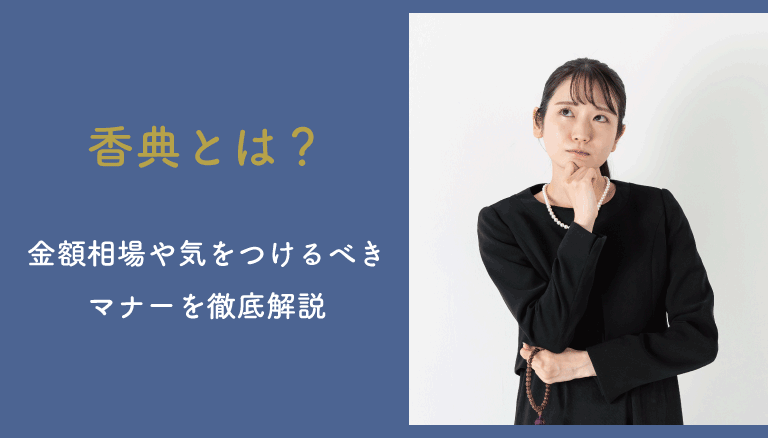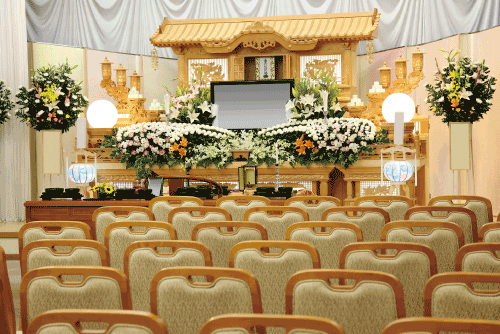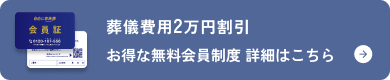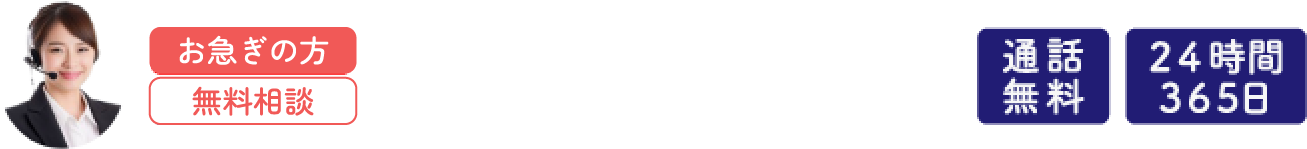お通夜参列の心得:流れ、服装、香典、焼香、お悔やみの言葉
滞りなくお通夜に参列するために、一連の流れを事前に把握しておくと安心です。また、参列者として、服装や香典、焼香といった場面ごとのマナーを心得ておくことが大切です。
本記事では、お通夜に参列する際に守るべき服装、香典に関する作法、正しい焼香の方法を詳しく解説します。さらに、心温まるお悔やみの言葉の例文もご紹介しますので、参列者としての礼儀作法を身につけたい方はぜひ参考にしてください。
お通夜の流れ:7つのステップ
お通夜をスムーズに進めるために、主な流れを7つの段階に分けてご説明します。
●通夜の準備
喪主またはご遺族から、お通夜、葬儀・告別式の日時や場所などが参列予定者へ連絡されます。受付や案内、会計などを担当する場合は、参列者が到着する前に準備を行う必要があります。
●受付準備
参列者が訪れる前に、受付の準備を整えます。一般的に、受付開始はお通夜の30分~1時間前です。参列者は、会場に到着後、芳名帳に記帳し、受付で香典をお渡しします。
●遺族・親族・僧侶入場
お通夜開始の1時間ほど前にご遺族やご親族が、30分ほど前に僧侶が会場に到着します。ご遺族やご親族は控え室で待機し、僧侶が到着次第、喪主や世話役が挨拶をして控え室へ案内します。その後、それぞれが入場となります。
●開式
ご遺族、ご親族、僧侶の入場後、お通夜が始まります。開式時間は一般的に18時~19時頃が多いです。参列者は、開式の15分前までに到着しておくとよいでしょう。
●読経・焼香
開式後、僧侶による読経と、ご遺族や参列者による焼香が行われます。焼香のタイミングは、僧侶または会場スタッフの案内に従うことがほとんどです。なお、焼香の開始時間は宗派によって異なる場合があります。
●閉式・通夜終了
読経と焼香が終わると、喪主がご遺族を代表して挨拶を述べ、その後、お通夜は閉式となります。
●通夜振る舞い
お通夜後には、参列者へ食事やお酒が振る舞われます。これは、ご遺族や参列者が故人を偲び、思い出を語り合うための時間です。参列者は、一口でも箸をつけるのが礼儀とされています。翌日には葬儀・告別式が控えているため、喪主やご遺族は通夜後も準備に追われます。参列者は長居を避け、ご遺族への配慮を忘れないようにしましょう。
参列者として守るべきお通夜のマナー:身なりについて
お通夜に参列する際は、服装をはじめとする身だしなみに注意が必要です。以下に、服装、アクセサリー、髪型など、身なりのマナーについて解説します。
服装のマナー
お通夜の参列者の服装は、基本的に喪服を着用します。男性と女性それぞれに適切な服装を確認しましょう。
●男性の場合
光沢のない黒色の無地スーツが一般的です。ジャケットはシングル・ダブルどちらでも構いません。パンツは、裾上げされていないシングル仕上げのものを選びましょう。ワイシャツは白無地のレギュラーカラーが基本です。色柄物やボタンダウンシャツは避けます。ネクタイは、光沢のない黒無地のものを着用してください。ベルトや靴下も黒無地のシンプルなものを選びましょう。バックルが目立つものや蛇柄などの派手なベルト、金具飾りのある靴は避けるのが賢明です。
●女性の場合
光沢のない黒色のアンサンブル、ワンピース、パンツスーツなどが一般的です。スカートは膝が隠れる程度の丈、またはそれより長いものを選びましょう。夏場でも肌の露出を抑えるため、トップスは五分袖までのものが適切です。ストッキングは、30デニール以下の黒色の薄手のものが推奨されます。厚手のタイツは避けるべきです。パンプスは、布製または革製のものが適切です。エナメル素材やヒールの高いもの、ミュール、サンダルはお通夜の場にふさわしくありません。
●アクセサリーや小物
お通夜では、光る素材のアクセサリーや小物は避けるのが原則です。金色の結婚指輪や複数のピアスなどは、参列前に外しておきましょう。ただし、シルバーのシンプルな指輪や、一粒の白いパールのピアスやネックレス、指輪であれば問題ありません。しかし、地域や世代によってはアクセサリーを身につけないという考え方もあるため、参列前に確認しておくとよいでしょう。
●メイクや髪型
メイクは派手にならないよう、ナチュラルメイクを心がけましょう。濃いアイシャドウや派手な口紅は避け、透明マスカラや元の唇の色に近い控えめな色の口紅を使用します。髪型も、派手なヘアアクセサリーを避け、落ち着いた印象になるようにまとめましょう。
数珠の選び方
数珠には、108個の珠を持つ本式数珠と、珠数を減らした略式数珠があります。素材は木や石が一般的で、色や種類も様々です。略式数珠は、珠数が少ないため持ちやすく、どの宗派のお通夜でも使用できます。ただし、宗派によって数珠の形が異なる場合があるため、事前に確認しておくと安心です。
お通夜での香典マナー
お通夜に香典を持参する際には、香典袋の選び方や書き方などのマナーを守ることが重要です。
●香典袋の選び方
香典袋の表書きには、御霊前、御香料、御香典、御悔、御榊料、玉串料、御花料、志などがあります。仏式では、四十九日までは「御霊前」、四十九日以降は「御仏前」または「御佛前」を用いるのが一般的です。仏式用の香典袋には蓮の花が印刷されていることが多いですが、神式やキリスト教式用には印刷のないものを選びましょう。キリスト教式用には、右上に十字架が印刷されたものを用いるのが一般的です。
●香典袋の書き方
香典袋には、表袋の上段に表書き、下段にご自身の名前を、内袋には金額と住所を記載します。「御霊前」は多くの宗派で用いられますが、浄土真宗では亡くなったその日に仏様になると考えられているため、「御霊前」の使用は避けるべきです。
●香典の金額の目安
香典の金額は、故人との関係性やご自身の年齢によって異なります。一般的な目安は以下の通りです。
- 親族: 祖父母:1万円~5万円、親:5万円~10万円、兄弟姉妹:3万円~10万円、叔父・叔母:5千円~3万円、その他の親戚:5千円~2万円
- 友人・近所: 友人・その家族:5千円~1万円、隣人・近所の方:3千円~1万円、その他の知人:3千円~1万円
- 職場・仕事関係: 上司・部下:5千円、社員の家族:5千円、取引先関係者:5千円~1万円
- 勤務先の社員やその家族へ包む場合は、ご自身の年齢に関わらず一律5千円が目安となります。
●香典を渡す適切なタイミング
香典は、受付を済ませた際に渡すのが最も適切なタイミングです。受付で記帳後、その場で香典を差し出し、「この度はご愁傷さまでございます」などのお悔やみの言葉を添え、深々と一礼しましょう。受付がない場合は、ご遺族に直接お渡しするか、会場スタッフや世話役の方にお渡しすることが多いです。自宅で家族葬が行われている場合は、ご遺族に挨拶する際、または仏前にお供えする形で渡すとよいでしょう。お通夜の規模や状況によって渡し方やタイミングが異なるため、事前に確認しておくことが大切です。
●香典の渡し方の作法
香典を渡す際は、袱紗(ふくさ)から取り出して渡すのが正式な作法です。袱紗を右手に乗せ、左手で包んでいる袱紗を開き、香典を両手で持って、表書きが相手に読めるように向きを変えてからお渡しします。袱紗がない場合は、ハンカチで代用しても構いません。香典を包んでいた袱紗は、受付の台に置いておきましょう。自宅でお通夜が行われている場合は、仏前に香典を供える形で渡すことがありますが、この際も表書きがご自身から見て読める向きにして供えるのが基本です。
●香典を渡す際の言葉遣い
香典を渡す際には、「この度はご愁傷さまでございます」といった簡潔なお悔やみの言葉を添えるのがマナーです。故人のご家庭の宗派によって死生観や教えが異なる場合があるため、事前に宗派を把握しておくと、より適切な言葉遣いをすることができます。
通夜での正しい焼香の作法
お通夜では、参列者一人ひとりが焼香を行います。焼香の作法は、葬儀の形式によって異なります。
●立礼焼香の場合(椅子席の葬儀)
椅子に座って参列する形式では、立礼焼香が一般的です。まず、祭壇に近づき、ご遺族に一礼します。香炉の前まで進んだら、故人に一礼します。香を軽く指でつまみ、顔のあたりまで持ち上げてから香炉にくべます。合掌し、頭を下げて故人を偲びます。その後、数歩下がり、ご遺族に一礼してから自席に戻ります。
●座礼焼香の場合(畳敷きの葬儀)
畳敷きの会場で行われる場合は、座礼焼香となります。焼香の流れや作法は立礼焼香とほぼ同じですが、移動の際は中腰の低い姿勢で行い、焼香は正座で行います。他の参列者の邪魔にならないよう、低い姿勢を保って移動することが大切です。
●回し焼香の場合(小規模な葬儀場や自宅)
自宅や小規模な葬儀場などで行われる場合は、回し焼香となることがあります。香炉がご自身の前に回ってきたら、軽く頭を下げます。香炉を膝の前に置き、合掌します。香を指で軽くつまみ、顔のあたりまで持ち上げてから香炉にくべます。再度合掌し、頭を下げて故人を偲び、次の人に香炉を回します。
●焼香の順番は遺族・親族から
焼香は、一般的に故人と血縁の近い方から順番に行われます。お通夜の席順は故人との関係性によって決められていることが多く、その席順に沿って焼香を行う場合があります。喪主や会場スタッフから案内があることがほとんどですので、詳細な順番を事前に把握していなくても問題ありません。ご遺族・ご親族内では、配偶者、子、兄弟姉妹、その他の親族という順になります。関係性の深さが判断しにくい場合は、年長者から順に行います。
●香炉の前での動作は静かに
香炉の前では、一礼や香をつまんでくべるなどの動作を、静かに丁寧に行うことが重要です。香炉の前での動作だけでなく、席を離れたり戻ったりする際も、静かに移動するように心がけましょう。
●数珠の使い方に注意
焼香の際には、数珠を持参するのがマナーです。数珠の使い方は、左手に房を下にして持ち、右手で焼香を行うのが一般的です。通常は左手の四本の指に数珠を通しますが、長い場合は二重にし、短い場合は親指と人差し指の間にかけます。ただし、宗派によって数珠の形が異なるため、故人のご家庭の宗派に合わせて数珠を選ぶのが望ましいです。数珠はご自身の身代わりと考えられているため、人に貸したり、雑に扱ったりすることは避けるべきです。
お通夜でのマナーに不安がある場合は、葬祭ディレクターなどの専門家に相談することもできます。
お通夜でかけるべきお悔やみの言葉
お通夜の場で、どのような言葉をかけたらよいか迷う方もいるかもしれません。ここでは、お悔やみの言葉の例文と、避けるべき言葉をご紹介します。
●お悔やみの言葉の例文
一般的なお悔やみの言葉は、「この度はご愁傷さまでございます。心からお悔やみ申し上げます」です。その他、「このたびは本当に残念でなりません。お力落としのことと存じますがどうかご自愛ください」「このたびは思いがけないことで、さぞお力落としのことと存じます」といった言葉も用いられます。
配偶者を亡くされた方には「このたびは誠にご愁傷さまでございます。奥様(ご主人様)のお悲しみもいかばかりかと存じます」、お子様を亡くされた方には「このたびはご愁傷さまでございます。ご両親の悲しみを思うと胸が痛みます」など、故人とご遺族の関係性に合わせて言葉を選ぶとよいでしょう。故人のご冥福を祈る気持ちや、ご遺族への心遣いを伝えることが大切です。
●お通夜で避けるべき言葉
お通夜の場では、忌み言葉やご遺族の負担になる言葉、故人の家の宗派に合わない言葉は避けるべきです。忌み言葉とは、不幸が繰り返されることを連想させる「重ね重ね」「再び」といった重ね言葉や、「死ぬ」「死亡」といった直接的な表現を指します。
お悔やみの言葉を受け止めるご遺族は、心身ともに疲弊していることがほとんどです。励ましの言葉も、状況によっては負担に感じさせてしまう可能性があるため、相手の気持ちに寄り添い、尊重する姿勢が大切です。
また、宗派によっては特定の言葉が忌み言葉とされている場合があります。例えば仏教では、「浮かばれない」「迷う」といった言葉は、故人が成仏できないことを連想させるため避けるべきとされています。神道やキリスト教では、「供養」「冥福」「成仏」といった仏教用語は不適切となる場合があります。
●お悔やみの言葉を伝えるタイミング
お通夜でお悔やみの言葉を伝えるタイミングは、受付時と、お通夜の会場での2回が考えられます。受付では、後にも参列者が並んでいる場合があるので、簡潔に伝えるようにしましょう。会場では、ご遺族に直接お悔やみの言葉を伝えます。ご遺族は心身ともに疲れていることが多いので、相手の気持ちに寄り添った温かい言葉を選びましょう。
まとめ
お通夜の流れは、会場の規模や故人のご家庭の宗派によって異なる場合があります。焼香の作法も、立礼焼香、座礼焼香、回し焼香と形式によって異なります。参列者は、黒色のシンプルな服装を選び、派手なアクセサリーや光るものを身につけるのは避けることが大切です。お悔やみの言葉や、それを伝えるタイミングなども事前に把握しておくと、失礼のない参列ができるでしょう。
自由に家族葬では、ただ安いだけでなく年間20,000件以上の葬儀実績を誇るグループとして、終活サポートや葬儀の事前相談から、葬儀後のアフターサポート(法事・仏壇・仏具の手配、墓地・墓石、遺品整理など)まで幅広く対応しています。
お通夜や葬儀に関して不安なことがある場合は、自由に家族葬に相談ください。24時間365日お客様のお問い合わせにお応えします。